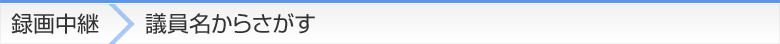|
|
1 災害時の水の確保
(1)磐田市の水の備蓄について
① 本市の断水に備えた水の備蓄の基本的な考え方と、防災拠点の非常用飲料水の備蓄状況について伺う。
② 避難生活の長期化を余儀なくされている能登半島地震の被災地の現状から、本市の水の備蓄状況の課題とその対策を伺う。
(2)飲料水の分散備蓄について
① 断水の長期化に備えた非常用飲料水を、被災時の道路事情などに左右されず迅速に避難者の手に届けるため、避難所ごとの分散備蓄を検討されたいと思うが、見解を伺う。
(3)断水時の給水計画について
① 磐田市地域防災計画の地震・津波災害対策編には「地震発生後約8日を目途に仮設共用栓等を設置し、最低限の生活に必要な水を供給するよう努める」とある。その間の給水車による給水拠点となる配水場は市内に何箇所あるのか、その総貯水量と併せて伺う。
② 地域防災計画には「飲料水の確保が困難な地域に対し給水拠点を定め、給水車等により応急給水を行う」ともある。磐田市の給水車の保有台数と、受援体制を勘案して、想定される災害での応急給水を十分賄えるとの考えか、所見を伺う。
③ 市内の小中学校などに給水タンクが設置されている。小中学校は災害時に避難所となるが、給水タンクがない施設もあるように見受けられる。配置の状況と、今後さらに整備する考えがあるか伺う。
(4)学校プールの水の活用について
① 災害時に避難所となる市内の小中学校で、生活用水としてプールの水の活用が考えられるが、見解を伺う。また、災害時にはプールの水が手洗いや食器洗い、洗濯などの生活用水に使えることについて、地域の自主防災会に周知されているか伺う。
2 上下水道等の耐震化
(1)磐田市の水道施設の耐震化について
① 厚生労働省の統計で、基幹管路と呼ばれる水道管の、その地域で想定される最大規模の地震に耐えられる割合を示す「耐震適合率」が、令和3年度末で全国平均の41.2%に対し磐田市は73.4%、地震で継ぎ手が外れない構造の耐震管率では磐田市は54.9%となっている。これまでの耐震化の概要と、それぞれの達成率の評価を伺う。
② 能登半島地震では、水源に近い主要施設の損傷が断水の広域かつ長期化の大きな原因といわれている。市所有の井戸水源からの導水管や各配水場への送水管、配水場施設の耐震対策の経過と現状について伺う。
③ 急激な人口減少社会を迎える中で、老朽管の更新と一体的に取り組んできている水道施設の耐震化の課題と、今後の方針を伺う。
④ 本市は公共下水道総合地震対策計画(第2期)を策定しているが、計画にある処理場やポンプ場施設の耐震化、また市内の1次緊急輸送路と各防災拠点を結ぶ2次緊急輸送路、及び市指定緊急輸送路の地震によるマンホールの浮上防止対策の進捗状況を伺う。
⑤ 能登半島地震を受け、被災地の現地調査などを基に第2期計画の事業の追加や優先順位、実施時期の見直し等が今後あるのか伺う。
(2)防火水槽の耐震化について
① 磐田市内に設置されている防火水槽の基数と、そのうち耐震性貯水槽の基数を伺う。
② 消防水利施設整備事業により毎年ほぼ4基ペースで設置されている耐震性貯水槽の、新規設置と老朽化などによる更新の比率を伺う。
③ 耐震性貯水槽の基本素材と、どれほどの震度に耐えられる構造なのかを伺う。
(3)緊急輸送路に関連する耐震化
① 地震により通行不能となった緊急輸送路を補完する周辺道路上の、橋梁の耐震化の進捗状況を伺う。
② 緊急輸送路沿いのブロック塀の撤去の状況を伺う。 |
 |
|
|
1 南海トラフ地震の臨時情報に伴う事前避難について
(1)誰に避難を呼びかけるか。
① 気象庁から南海トラフ地震の臨時情報「巨大地震警戒」が発表された場合の、本市の事前避難の対象地域と対象者について伺います。
(2)どのように避難を呼びかけるか。
① 事前避難の対象地域、対象者への情報伝達の方法について伺います。
(3)どこへ避難してもらうか。
① 事前避難の避難先と、避難所の指定について伺います。
② 学校やその他の公共施設、民間の宿泊施設を避難所とする場合の課題をそれぞれ伺います。
(4)どのように避難してもらうか。
① 避難対象地域外の避難所への移動はどのように想定しているか伺います。
(5)事前避難期間中の教育、保育施設について
① 事前避難となった場合、対象地域の幼稚園や保育園、こども園、小中学校は休園・休校となるのか伺います。
(6)事前避難の解除
① 事前避難を解除する際の周知方法について伺います。
2 防潮堤完成後の津波防災
(1)津波災害警戒区域等の指定について
① 本市にとっての津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域の位置づけと、指定後の対応について伺います。
(2)防潮堤と津波災害警戒区域等について
① 防潮堤の完成と津波浸水想定区域、津波災害警戒区域等の設定との関係について伺います。 |
 |
|
|
1 気候変動下の防災対策について
(1) 防災対策の推移と市民理解について
① ここ数年の、気候変動に対応して大きく変わった防災気象情報や避難情報について、市民への周知や啓発は、どのようになされてきているか伺います。
② 磐田市水防計画書にある、レベルに応じた配備体制と要員、配備基準などで、抜本的な見直しを図ってきたこと、また新たに明らかになった課題について伺います。
③ 警戒レベル3で「高齢者等避難」、レベル4で「避難指示」など、昨年5月の災害対策基本法改正でより早い段階での避難となったことで、対象区域の防災対策にどのような影響があるかを伺います。
(2) 避難情報発令の判断について
① 本市の場合、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域などで、避難情報の発令の判断が難しいと思われるような要因があるのか伺います。
(3) 防災情報の集約について
① 気候変動の時代に対応した河川防災の、“情報弱者”のための対策について伺います。
② 気象庁等が発表する防災気象情報と市の対応、住民が取るべき行動について、5段階の警戒レベルに集約・整理して、台風接近時などに磐田市公式ホームページなどを使い目立つ形でリアルタイム表示できたらと考えます。また、磐田市公式ホームページの「防災」と防災リンク集を、互いに関連付けて一覧表示をと考えますが、それぞれ見解を伺います。
2 天候急変と要配慮者の避難について
(1) 避難確保計画と個別計画について
① 本市の地域防災計画に定めた要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について、洪水浸水、土砂災害それぞれの対象となる施設数と作成状況を伺います。
② 昨年5月から自治体の努力義務となった在宅の避難行動要支援者の個別計画の作成について、対象者の人数と作成率、及びその達成度の評価について伺います。
(2) 福祉避難所の現状と課題について
① 市内の福祉避難所の指定状況と、必要となる人手や備蓄などの支援体制について伺います。
② 災害時の福祉避難所の位置付けと、一般の指定避難所との関係についての住民への周知、また災害時に予想される直接避難の受け入れや対象者の特定など、運用面での課題について伺います。 |
 |
|
|
1 子育て支援について
(1)子育て支援を通した世代間交流
① 少子高齢化の中で、子育て支援と高齢者福祉の趨勢をどう捉えているか伺います。
② 子育て支援を通して子育て世代とシニア世代の交流を図ることについて見解を伺います。
(2)子育て支援センターの今日的役割
① 市内10カ所の子育て支援センターでの、民間ボランティアのかかわりについて伺います。
② 子育て支援センターの運営にシニアの皆さんをはじめ多世代のボランティアが積極的に加わり、豊富な育児経験を生かせる仕組みづくりをと考えますが見解を伺います。
(3)幼保再編と子育て支援センター
① 昨年7、8月に実施した保護者アンケートの結果の評価と、(仮)磐田市幼児教育・保育推進計画への反映について伺います。
② 幼保園・こども園と子育て支援センターの連携について伺います。
③ 空白地域となっている見付地区における子育て支援センターの方向性について伺います。
2 磐田市学校施設の更新計画
(1)これからの施設整備サイクル
① 財政負担の軽減と事業費の平準化を目的とした「これからの施設整備サイクル」において、「建替え」「長寿命化改修」「大規模修繕」それぞれの考え方と判断基準を伺います。
② 更新計画には「学府の形態も考慮し、子どもたちにとってより良い教育環境の整備を行う」とあります。学府一体構想で「既存施設のまま小中一貫教育を推進し、社会教育施設を含む」とする施設分離型学府一体校の、施設整備サイクルにおける課題や考えを伺います。
3 地域コミュニティに生かせる空き家、空き店舗対策
(1)空き家、空き店舗情報の提供
① 商店街のにぎわい復活のため、空き店舗の賃貸借など流動化を促す物件情報の提供が必要と考えますが、見解を伺います。
② 空き家対策に取り組む地域のNPOなどに対する、市が保有する物件情報にかかる行政データの提供の可否と、課題を伺います。
(2)ビッグデータの活用について
① 匿名化した行政データや携帯電話のGPS情報など、リアルタイムで得られる膨大なデータを、まちづくりの政策立案とその検証に積極活用していく考えについて伺います。 |
 |
|
|
1 文化財を活用したにぎわい創出
文化財を生かした地域振興を促す文化財保護法改正により、市町村への権限移譲とともに、それまでの保護中心から保存と活用の両立へと文化財行政が大きな転機を迎えました。少子高齢化と人口減が背景とされ、目が行き届かなくなりつつある文化財の滅失や散逸を防ぎ、未指定を含めた文化財をまちづくりに生かしつつ、地域社会が総がかりでその継承に取り組んでいく必要が叫ばれています。一例として、高齢化が進む見付地区でも、主に中心部にある数多くの史跡や歴史的建造物をまちづくりにいかに活用し、人のにぎわいを取り戻すかが問われています。そこでいくつか質問します。
(1)「保存と活用」の具体化
① 平成31年の文化財保護法改正以降の、本市のこれまでの取組について伺います。
② 法改正に基づく文化財の活用について、今後のどのような展開を考えているか、ビジョンを伺います。
③ 文化財を活用した郷土学習の推進について伺います。
④ 保存と活用を担う専門的な人材の確保や、地域のNPOなど支援団体との連携、協力について伺います。
⑤ 国指定史跡の旧見付学校など、公開による施設の摩耗や損傷が避けがたい歴史的建造物の、活用と保存のバランスをどう図るかを伺います。
(2)活用を通した観光振興
① 地域の商店のにぎわい復活や観光振興につながるような、文化財の活用の今後の在り方を伺います。
② 国の重要無形民俗文化財である見付天神裸祭の観光客や、年間を通した見付天神社への参拝客のための、高齢者や体が不自由な方にも配慮した駐車場、さらに大型バスが安全に通行できる交通アクセス整備について伺います。
2 緑茶の地産地消
若者のお茶離れやペットボトル茶の普及によるリーフ茶の需要低迷で、静岡県が産出額(2019年統計値)で長く続いた首位の座をライバル鹿児島県に明け渡すなど、茶業界がかつてない苦境に立たされています。一方で昨年来、全国の大学や研究機関で、新型コロナウイルスに対する緑茶の不活性化(増殖阻害)作用に関する発表が相次ぎ、まだ基礎研究の段階ではあるものの、withコロナの時代の「新しい生活様式」を支える緑茶の役割に大きな期待が集まっています。そうした複眼的な視点から、磐田茶の現況と、本市の取組について質問します。
(1)茶生産者の経営環境と新規需要開拓
① 経営環境が厳しさを増す茶生産者の動向と、茶園転換支援事業の状況、今後の見通しについて伺います。
② 磐田茶の地産地消と需要拡大のためのここ数年の取組、その成果について、総括的な評価を伺います。また、今後の推進にあたっての課題を伺います。
(2)「新しい生活様式」と緑茶
① 「新しい生活様式」の一環として、地産地消の新たなルート開拓と大量需要が見込める「お茶うがい」を、スティックタイプ(個包装)の粉末茶の形で市内の小中学校への導入や高齢者施設、介護施設などへの普及を図る考えについて伺います。
② 県内屈指の早場茶が育つ日照時間の長さや機械化が容易な立地など、産地の特性と磐田茶の持ち味を生かした今後の消費拡大策を伺います。 |
 |